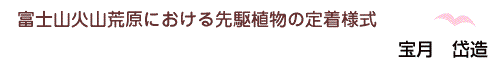
木々が生い茂った深い森を見ていると、この森が、何百万年もの太古の昔から深い森であったような錯覚に陥る。しかし実際には、ほんの少し前まで、大きな天変地異で生じた荒原だった例も少なくない。そもそも森林は、もとを突き詰めてたどれば、木立一本無い寂寞とした荒野から始まっている。植物の種子も切り株も何もない荒野から始まり、森林へと変化する場合、その変化の過程を一次遷移と呼ぶ。一次遷移が始まる代表的な場所としては、火山の大爆発によって火山礫が全ての植物を埋め尽くしてできた火山荒原や、海底が隆起してできた陸地などがあるが、そんな植物の痕跡が全くないところでも、何百年も経つとどこからともなく植物がやってきて定着し(先駆植物と呼ばれている)、やがて草原ができ、さらに樹木が定着して、最終的には鬱蒼とした森林になったりもする。
さて現在私たちは、この一次遷移に焦点を当ててそこでの先駆植物の定着メカニズムを調べており、最終的には、それに則った生態系保全法を打ち立てたいと考えている。自らに投げかけている当面の問いは、「定着する先駆植物の種子は、どこからやってくるのだろうか?」というものである。この答えを出すには、定着している植物の母親を見つけ出せばよい。とはいえ、母親探しはそう簡単ではない。「他人のそら似」とか「似てない親子」というのも少なくなく、ただ見比べるだけで親子は判別できるものではない。幸いにも最近になって、親探しが比較的確度高く出来るようになってきた。「DNA鑑定」である。これは親子認知裁判や犯罪調査に頻繁に利用されている技術であるが、植物にも適用できる。この方法によって、これまで解らなかった先駆種の定着の様子がかなり解ってきた。
一次遷移の典型的一例が、富士山の南東斜面で観察できる。かつてこの斜面は、大噴火により火山礫や火山灰で数メートルから十数メートルの厚さに埋め尽くされた。1707年の宝永大噴火である。これにより、噴火以前にそこで生息していたあらゆる植物が息絶えたと言われている。それから300年、斜面の大部分は依然として荒涼としているが、よく見るとあちこちでパッチ状に植生が回復しつつある。全体としては、あたかも斜面をはい上がるように、高度の低い麓から上へと徐々に植生が回復している。斜面上部は植生が定着してから間もない状態、斜面下部は植生が定着してからかなり時間が経った状態にあるので、斜面の上から下へのラインをたどれば植生回復の時間経過が想像できる。まず何もない火山荒原の上に、イタドリ、オンタデ、フジアザミといった比較的根を深く伸ばす先駆草本種が定着する。このうちイタドリは、地下茎を八方に伸ばして栄養繁殖し、大きな植生パッチに発達する(写真)。


(左)イタドリのパッチ
(右)ミヤマヤナギ
イタドリのパッチが形成されると、火山礫上に直接定着できない弱い種にとっても比較的安全な環境が整い、そこに様々な草本種が定着する。やがて、草本種に加えて、ミヤマヤナギといった先駆木本種が定着するようになり、森林への第一歩が標される。
最初の問いに戻ろう。「定着する先駆植物の種子は、どこからやってくるのだろうか?」富士山のミヤマヤナギについて「DNA鑑定」をしてみると、これまで解らなかった定着の仕組みが見えてくる。初めに多数の遠く離れたミヤマヤナギの母親から種子が飛んできて定着し、一旦定着した樹が成熟して種子を着けるようになると、その周辺に多量の種子を散布していわば同じ家系の「集落」をつくることがこれまでに解った。遠く離れた多様な母親からの種子の定着は、ミヤマヤナギ集団内の遺伝的多様性を高めることになる。また定着した樹による周辺への多量の種子散布は、おそらく多様性は低めるが定着のスピードを加速するはずである。遺伝的多様性を確保しつつ定着を速めるという、自然の絶妙なバランス感覚というべきかもしれない。
一方、富士山で植物の定着の調査をしていると、パッチの中や縁に多様なキノコが大量に発生するのに気がつく。注意深く丹念に調べてみると、発生するキノコの多くは外生菌根菌と呼ばれるタイプの菌類で、ミヤマヤナギの根に共生していることが解った。菌が共生すると根に外生菌根と呼ばれる独特の共生構造ができ、そこから菌糸が土壌中に広がって発達する。ミヤマヤナギは、光合成で作った有機物を、外生菌根を通して菌に分け与え、菌はそれを元手にキノコを作る。一方外生菌根菌は、土壌から吸収したリン酸などの養分を、外生菌根を通してミヤマヤナギに分け与える。養分が少ない火山荒原のミヤマヤナギは、それによって成長や生存に必要な養分を得る。実際、発生したキノコから分離した菌を人工的にミヤマヤナギの苗に共生させると、苗の成長が目に見えて良くなる(写真)。外生菌根菌は、富士山に定着する先駆樹木の成長や生存を、地下で人知れず助けているのである。

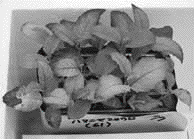
(左)共生していないミヤマヤナギ苗
(右)共生しているミヤマヤナギ苗
外生菌根菌の共生機能:ミヤマヤナギ苗は、富士山のハマニセショウロと共生して3ヶ月もすると、成長が目に見えて良くなる。(写真:奈良一秀博士提供)
ここでもう一度ミヤマヤナギの時と同様の問いを発してみよう。「定着する外生菌根菌の胞子は、どこからやってくるのだろうか?」ここでもまた「DNA鑑定」を使ってキノコ同士の近親関係を調べると、目には見えない菌の定着の様子が見えてくる。ものすごい量のキノコを作るハマニセショウロという菌は、これまたものすごい量の胞子を飛ばす。「DNA鑑定」の結果、この菌では、初めに多数の遠く離れたキノコから飛んできた胞子が定着した後、そこから土壌中に菌糸を伸ばし、出会った根に新たな菌根を次々に作りながら占有範囲を広げていくことが解った。多様な胞子の定着は、火山荒原でのハマニセショウロの遺伝的多様性を高め、一方で菌糸の伸展による占有範囲の拡大は、多様性は低めるが定着のスピードを加速する。なにやらミヤマヤナギの場合とよく似ている。
富士山火山荒原には、ほかにも多種の先駆植物や菌根菌が、様々な生活パターンで生育している。すべての種がミヤマヤナギやハマニセショウロのような定着の仕方をしているとは限らない。多様な生活パターンに応じて多様な定着パターンがあるのだろう。今後、2種以外の定着パターンも「DNA鑑定」によって明らかにし、火山荒原での植物と外生菌根菌の定着の全体像を明らかにしたいと思っている。
ところで、富士山で研究する者の一人として、最後に一言コメントしたい。富士山火山荒原の麓付近では、植生回復のための苗木植栽という「自然保護」活動が行われている。「DNA鑑定」で解ったように、ミヤマヤナギやハマニセショウロは、多様性と定着スピードのバランスをとりつつ定着していた。私たちの知らない巧妙な仕方で定着している他の種もいるだろう。人工植栽に際しては、こうした様々な定着パターンによって出来上がった遺伝的多様性や遺伝的地域性を乱さないように、気を配る必要がある。この活動では、その点は大丈夫なのだろうか? もしそうした配慮がなければ、善意の植栽も取り返しのつかない自然破壊になってしまう。また、そもそも富士山火山荒原は、一次遷移という人為を超えた雄大な自然の営みを直に目にできる貴重な場である。人工植栽などしなくても、ここでは自然の力だけで、ゆっくりと、しかし確実に植生が回復しており、そのスピードが遅いとしてもその遅さ自体が富士山の本来の姿である。本来の自然を破壊する過度な人工植栽は控えてほしいと思う。富士山の自然は、人為を加えずしてこその自然である。公園化された富士山など見たくもないと思うのは、私だけだろうか?
(学際 15:16-20, 2005)
2005.11.21
宝月岱造